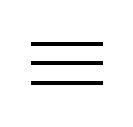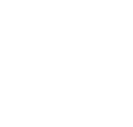Blogブログ
カプセルトイ
2025.05.12NEW
朝の情報番組でカプセルトイの第5次ブームという話題がやっていました。
第1次ブームは1983年の「キン肉マン消しゴム」、1985年の「SDガンダムの消しゴム」の時代。
第2次ブームはフルカラー、200円商品が出てきた1995年頃。
第3次ブームは「コップのフチ子さん」等の大人が興味を持つ商品を展開しだした2012年頃から。
第4次ブームはインバウンド需要の関係などから増加していった2018年頃から。
第5次ブームはコロナ禍による空きテナントの増加を解消するための方策として、
省スペースでも展開でき、初期投資が少なく抑えられること等から、
ショッピングモール等にカプセルトイの集まった店舗が拡大していったことが背景にあると言っていました。
確かに色々なところでカプセルトイの集まったところを見る機会が増えましたし、
どこの店よりもにぎわっているイメージがあります。
自分自身、カプセルトイをすることが好きなので、買い物に出ると立ち寄ります。
子供のころの記憶として、キン肉マンは世代的に少し上なのであまりやっていませんでしたが、
SDガンダムやディフォルメした怪獣の消しゴムはかなりいっぱい持っていました。
同時期に流行っていたビックリマンシールとかよりも、こっちの方が好きだった記憶があります。
第2次ブームはあまりわからないですが、第3次~第5次は途切れない感じで回していると思います。
ガチャの魅力は手を出しやすい価格帯、どれが出るかわからないドキドキ感、
集めやすい種類数からのコレクター欲のバランスにあると思います。
市場急拡大の背景には、3Dプリンターの普及で少量の商品の生産が容易になり、
工場を通さなくても商品も世に出すことができる。
大量生産のプロセスを追わなくていいので、開発期間も短く、コストも少なく済む。
商品自体が小さいもので、店先のスペースでもいいので置く場所がいっぱいある。
どんどんトライする流れができ、多種多様な商品展開することで、多種多様な商品体系が出来る。
誰でも何かは気になるものが置いてある空間になり、市場が発展していく。
時代に合ったサイクルで、かなり好循環の条件がそろっているので、
これはブームと呼んでいいのかどうかわからなくなります。
しいて言えば、価格がどんどんあがってきていることが懸念くらいですかね。
心理的に300円は迷わずに使ってしまう額らしく、100円玉も3枚くらいは残っていることが多いですが、
400円、500円となってくると、冷静になってしまうかもしれません。
最近うちで購入したカプセルトイは、コンバースのスニーカー(白オールスター・箱付き)、
トイストーリーに出てきた箱入りのバズライトイヤーやミャクミャク、
アーティストのダイスケコンドウさんのフィギアだったりです。
小銭を入れて、ガチャガチャ回す。
あのアナログ感と、何が出るかのワクワク感、コレクター欲が混ざってしまっては、
当分の間はカプセルトイの魅力からは逃れられそうにないです。
タナカマサヒロ